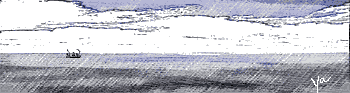
ついに白灯台まであと五十メートルのところまで近づいた。
またしても速くなってきた潮の流れに負けないように三人はバタ脚に力を込めて進んでいった。どうやら潮流がいったん防波堤にぶつかるせいで、白灯台のまわりは潮の流れが強くなっているらしい。
白灯台の周囲では十数人の男たちが釣り糸を海に垂らしていて、釣り人のひとりが三人に向かってしきりになにか叫んでいた。だが防波堤に打ち砕かれる波の音に遮られて、何を言っているのか亮一たちには聞き取れない。
慎二がその男に手を振った。
「ほら、あっちも手え振っとるよ」慎二は嬉しそうに更に手を振った。
鉄也がチッと舌打ちした。
「慎二やめろよ、あっちへ行けって言うとんがだ、あのおっちゃん」
「えっ、なんで?」
「釣りしとるから、じゃまなんだろ」
亮一の目にも、男が犬や猫を追い払うようなしぐさをしているのがわかった。今にも石を投げつけてきそうな険しい顔にみえる。
三人は仕方なく白灯台を諦めて、岩瀬港を隔てた赤灯台に向かうことにした。潮流にまかせていけば二十分程でたどり着けそうな距離だった。
港への入口にさしかかると、急に海は透明度を失い、漆累の無気味な色に変わった。水温が急激に低くなり、気を抜くと躰に震えがきそうだった。陽射しは相変わらず厚い雲に遮られていて、落ち込んでうなだれている慎二の日焼けした腕には、わずかに鳥肌が立っていた。
港から出てきた漁船が通り過ぎていった。乗っていた漁師が不機嫌な顔で三人を見下ろしていった。エアーマットにつかまっている亮一たちが流されているとは、誰も思っていないようだった。
「慎二、落ち込むなよ」鉄也が慎二の肩に手をまわして言った。「大人なんて自分勝手で、こっちのことなんか何にも考えとらんがだから」
結局、赤灯台にもたどり着けなかった。やはり釣り人がいたからだ。
三人は赤灯台をやりすごし、次に神通川の二百メートルもの河口を横切り、そうして初めて見る遠浅の海岸にやっとの思いでたどり着いた。
三人とも足がしびれてしまっていて立つことができず、這って砂浜に上陸すると、冷えきった鉢を暖かい砂の上に大の字に投げ出した。
亮一は何度も深呼吸しながら、大地のありがたさを背中一面で感じていた。
それからどれくらいまどろんでいただろう、亮一がふと気づくと、隣で気持ち良さそうに目を閉じている慎二の向こうで、鉄也が膝を抱えて海を見つめていた。
「帰らんとのう」亮一はぼんやりとつぶやいた。
「うん、帰らんとのう」鉄也が意外としっかりした声で答えた。
いつのまにか姿を見せている太陽が、大きく西に傾いていた。