母親が怒るのは、
家庭訪問の日であったり、通信簿やテストを返された日であったり、何気ない冗談を言った時であったり、母親が呼んでもすぐに返事をしなかった時であったり、母親のちょっとした失敗にえへっと笑った時であったり、場合によっては鉄也が嬉しそうにはしゃいでいる時であったりする。
家の外で怒ることはあまりない。しかしどなり声が隣近所にまで聞こえてくるので、亮一たちは鉄也の母親の激しい気性をよく知っていた。要するに鉄也の母親は、本人の機嫌の悪い時に、あらゆる理由をつけて鉄也にいらついた感情をぶつけているようであった。
母親は、鉄也が小学生になった頃から素手で殴ることはしなくなった。代わりに、ほうきや物差しで殴ったり、線香を押しつけたりするようになった。ロウソクを使おうとしたこともあったが、鉄也がすぐに吹き消すので使わなくなった。
そんな暴力と同時に凄まじいのが、「おまえ−−」から始まる罵声であった。
「 おまえ のせいで恥かいたじゃないか! おまえ みたいな奴は施設に入れてやっじゃ!
「 おまえ なんか産むんじゃなかった!
「 おまえ をそこまで大きくするがに、どんだけ金使うたと思うとる!
「 おまえ なんかうちの子じゃない。橋の下で拾うてきた子やじゃ。
「 おまえ を見とるとイライラしてくっじゃ。魚の腐ったような眼で見るな!
「 おまえ が悪いくせに、なんで泣くがよ!怒ってくれる親がおるだけでもありがたいと思え!
母親はいつもきまってそんな罵声を、思いつくまま鉄也に浴びせかけていた。そうやって暴力と罵声とで感情を発散しきるまで、繰り返し執拗に鉄也を虐待するのだった。
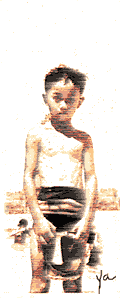
白灯台はすこしずつ近付いてきていた。
慎二は黙っていると不安なようで、テレビ番組のことを話題にして喋り続けていた。亮一は適当に相槌を打ってはいたが、頭の中では、夏休みに入る前のカエルの解剖の日のことを思い浮かべていた。
あの日、夜中にふと目を覚ますと、ふすまを隔てた両親の部屋から、めずらしく母の怒った声が聞こえていた。
「・・・だいたい子供ってのは天からの授かりものなのに、いくら自分の子だからって、あんなふうにせっかんして許されるもんじゃないちゃよ!」
亮一はその言葉で、母が鉄也の家のことを言っているのだとすぐにわかった。
「それにしても、あそこのお父さん、なんで鉄也ちゃんをかばってやらんのかねえ」
「いやあ、あのお父っちゃんのこたあ、気の弱い人ながや」
父は冷静に応えていた。
「だけど、隣近所のもんが耳を塞ぐほど息子がひどい目に合うとるのに、女房になんも言わんなんて!」
「まあ、あのおやじさんがなんか言ったところで、あのおっ母さん、包丁持ち出して、わしに文句あるがならこれで刺し殺せって言い出すんだから、どうにもならんのだろう。
−−このあいだ、わしも、男の子はいたずらするくらい元気があるほうがいいんだから、鉄也をあんまり叱ってやるなって言うたがだ。そしたらあのおっ母さん、自分の子供を可愛くない親なんかおらんちゃって言うがよ。そう言われりゃ、それ以上は何も言えんちゃ」
「そんな、子供が可愛かったら、カエルを解剖したぐらいのことでせっかんするはずないちゃ!」
「それがこうも言うがよ。親っちゃ子供叩いとったって、叩いとる自分の手のほうがもっと痛いもんだちゃって」
「嘘ばっかり!ほうきで叩いてるくせに!」
「しいっ、大きい声出すなよ。ボウヤが起きるねか」
「それにしても自分の子に、どうしてあんなひどいことができるのかねえ」
母の憤った大きなため息が聞こえた。
「そやのう、親の暴力をしつけだと勘違いしとるがかもしれんのう。もしかしたら、自分も同じように叩かれて育ったがかもしれん。それで自分の子も同じように叩いて従わせようとしとるがかもしれんなあ」
「だけど、自分が子供の頃辛い思いをしてたとしたら、自分の子供にだけはそんな思いをさせまいとするのが親の気持ちじゃないの!」母の声がまた尖ってきた。
「まあ、あの人は若くに鉄也を産んだからなあ。自分が精神的にまだ未熟なのに子供を産んでしまったから、親っていう自覚がもてないのかもしれんなあ」
「だけど、若くてもちゃんと育てている人だっていっぱいおるちゃよ」
「おい、だけどだけどって、おまえそんなにあのおっ母さんの悪口言って何になるがよ」
「だって、鉄也ちゃんがかわいそうだから、、、」
「あの人だってかわいそうながや。子供を可愛いがる喜びってものを知らんがだからな」
亮一は、鉄也がなぜ母親に怒られたのか気が付いた。父と母は、自分が解剖のことを自慢げに話したので、カエルの解剖のことが原因で鉄也がせっかんされたと思っているようだが、そうではない。
亮一たちは浜にカエルを埋めた後、鉄也の部屋を念入りに掃除して、鉄也のかばんとシャツもしっかり洗った。畳には血は落としてなかったし、血のついた手ぬぐいとベニヤ板は新聞紙に包んで洋介が持ち帰った。カエルのことではないのだ。
はじめから鉄也の母親が不機嫌になる日だったのだ。
亮一は、その日、お昼の校内放送の大失敗でしょげていた自分に、
「気にすんなよ。おれなんか、このテスト母ちゃんに見せたら、バコーンとボコーンで、びっくりしたな、もお、になるじゃ」と、明るくおどけてみせた鉄也の顔を思い出した。
鉄也は25点のテストがどんな結果をもたらすのか、あの時すでにわかっていたのだ。
どんなせっかんが待っているかわかっていたのに、オレを元気づけようとしてあんなこと言って・・・
その夜、亮一は心に誓った。オレだけは鉄也の味方でいよう。