十数軒の浜茶屋が一目で見渡せた。どうやら三百メートルばかり沖合まで来ているようだ。上空を薄っべらい羽毛のような浮雲がゆっくりと流れていく。海岸の方から飛んできた鳶が、亮一たちの頭上で興味ありげに何度か旋回して、また海岸へと飛んでいった。
「あれえ、なんか浮いとっぞお!」
少し先を泳いでいた鉄也が大声を上げた。
薄汚れて灰色がかった丸いものが海面に浮いていた。三人が近付いてみると、それはひとかかえ程の大きさに膨らんだセメント袋のようなものだった。
「なんやろ、これ」
亮一はなんだか気味が悪かった。
「浮き袋やろ」と鉄也。
慎二は呑気にエアーマットに乗っかったまま、片手でその袋をボコボコ叩きながら向う側に回り込んだ。
「わあ、太鼓みたいやじゃ。いい音すっちゃ」
袋がごろんと動いた。
「 ひ いぃぃぃ!」
突然慎二が悲鳴を上げ、のけぞった。そのとたん、バランスを失った慎二の躰は袋にぶつかっていき、そのまま海中へと転がり落ちた。
袋がまたごろんと大きく向きを変えた。ぱんばんに膨張した動物の死骸が、恨めしそうな顔で鉄也と亮一を見ていた。
「 わ あっ、ぶた!」
二人は同時に叫び、クロールのような犬かきのような無茶苦茶な泳ぎで一目散に沖に向かって逃げた。かなり豚から柾れたところまで逃げると、二人は慎二がエアーマットを引っ張りながら必死で追いついてくるのを待った。
すっかり息が切れてしまっていた三人はエアーマットを横にして並んでつかまり、改めてすこし右にずれたロシア船に向かってバタ脚で進んでいった。
「あ−びっくりした、なんであんなとこに豚がおったがやろ」
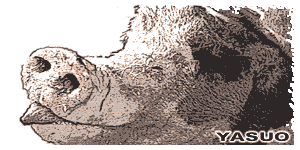
慎二は安心したのか、やけにはしゃいで言った。
「きっと朝鮮から流れてきた豚やじゃ!」鉄也が言った。
「中国の豚かもしれん!」慎二が負けじと言った。
「あの豚、浜にたどり着くかなあ」亮一もなんだかおかしくなってきた。
「たどり着いたら大騒ぎになるじゃ」
「うん、大騒ぎになるじゃ、なるじゃなるじゃ」
「豚のお化け屋敷つくれるじゃあ」
「豚のミイラつくれるじゃあ」
「豚汁つくれっちゃ」
三人はてんでに勝手なことを言い、大笑いしながら進んでいった。