鉄也は「うん、うん」と相槌を打ちながら慎二の話を聞いていたが、亮一はその噂を信じられなかった。そんなうまい話があるはずがないと思ったのだ。
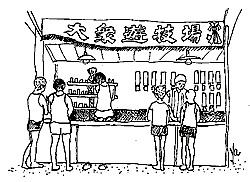
朝のラジオ体操が終わって、三人は浜茶屋「上海」の欄干に並んで座っていた。夏の盛りとはいえ、浜の朝は涼しくて、海からの風が潮の香りを運んでいた。
「船の外に階段ついとるねか、そこから船に上っていったらいいがだって」
慎二は眉を寄せた真剣な顔で声をひそませた。
「嘘つけえ」と亮一は言った。慎二が嘘を言う奴ではないことはわかっていた。誰かが嘘を言いふらしているのだろうと思った。
「いや、ほんとかもしれんじゃ。うちの父ちゃんも昔、港で外人にガムもろうたって言うとったから」
鉄也が亮一の顔を覗き込むようにして言った。
鉄也の大きく見開かれた眼はいつもの好奇心に満ちていた。慎二も亮一にぐっと顔を寄せて、何度も領いてみせた。
「なんだよ二人とも、真剣な顔して」
話の方向はもう決まったも同然だった。
「時間かかりそうだから昼から行こうよ」鉄也が力強く言った。
「行こ、行こ」と慎二が声を弾ませた。
亮一は沖に停泊している二隻のロシア船を見やった。両方とも浜から五百メートル以上離れているように見える。
「どっちの船に行く?」
「左側の船の方が近いかな」と鉄也。
「うん、左側のやつの方が近い、近い。階段も見える、見える」と慎二。
いつも遊んでいる上海の前からは出発できない。おっちゃんに見つかると、折角の計画が実行できなくなる恐れがあるからだ。
三人は昼飯の後集まると、上海の床下にサンダルやシャツを素早く隠し、人だかりをぬうようにして波打ち際を防波堤の方へと歩いていった。
「マイアミ」の前あたりまで来ると、目的のロシア船の船腹がちょうど真正面に見えていた。
「この辺からでいいな」鉄也が二人を振り返って言った。
このあたりは遊泳地域からすこし離れているせいか、二組の家族が浅瀬で遊んでいるだけで、海で泳いでいる人の姿はなかった。浜には打ち上げられたスイカの皮や、板切れが散乱していた。
慎二は、エアーマットという背丈ぐらいある長方形の青い浮き袋を持ってきていて、ごみのないところに寝かせると、準備体操を始めた。
「泳げるくせに、こんなもん持っていってどうすんがよ」
鉄也が屈伸運動をしながら慎二に言った。
「オレ、これまだ海で使うたことないから」慎二は照れ笑いを浮かべた。
「もしかして、こいつの上にいっぱいお菓子もらってきたりして」
亮一が冗談のつもりでそう言うと、「うん、それはおおいにありえるな」と鉄也はとたんに顔をほころばせた。
早朝には澄んでいた海も今は薄茶色に濁っていた。
この頃の海は、工業廃棄されるパルプかすや、海洋投棄される土砂を呑み込んですでに汚染されていた。しかし、亮一たちにとっては、この濁った海があたりまえの海の色だった。
三人は海に入ると無言でゆっくりと泳いでいった。鉄也と亮一の平泳ぎの後ろを、慎二が上半身をエアーマットに乗せて、足だけを使ってついてくる。強い陽射しのせいか海水は暖かく、亮一の耳元には両手で海面をかきわける時の静かな水音が心地よく聞こえていた。