浜の中ほどのカーバイトの道に沿って浜茶屋が並んでいた。横一列に十数軒並んだ浜茶屋はどこも同じような造りで、低い欄干のついた板の座敷と、その片側にちょっとした売店、脱衣所、シャワー室があるという簡単なものだった。
二人はいつもくる浜茶屋「シヤンハイ」の床下に入り込んだ。ゆるい傾斜に建っている浜茶屋の丸見えの床下は、海側から入り込むと子供の背丈程の高さがあり、浜の子供たちは時々こんなところを根城にして陽射しから逃れていた。
海に向かって座った亮一の目の前には、いつもの浜の風景が広がっていた。
海岸で出番を待っている貸しボート。海辺をコの字型に囲んでいる白くて丸いブイ。その遊泳地域の囲みの向こうに海面から突き出している錆びた鉄骨の飛び込み台。よじ登っている人々。そしてずっとずっと先の水平線の手前には、ロシア船が材木を山積みして停泊していた。
空は、今日も雲ひとつなく晴れ渡っていた。
「あっ、五十円見っけ!」
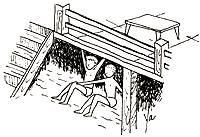
ぼんやりと砂をいじっていた鉄也が、銀色の大きな五十円玉を見つけた。
「えっ、うそ、すごい」
「あっ、ここにも」
鉄也は続いて十円玉をつまみ上げた。
すかさず亮一は天井の床板の隙間から上を覗き込んだ。
「上には誰もおらんじゃ」
客が別の日に上から落としたのに違いない。二人は床下を躍起になって探し、道側の狭いところも腹這いになって入り込み、全部で九十円もの硬貨を見つけ出した。思わぬ収穫に、二人は一気に元気を取り戻した。
その時、「お−い」と、どこからか大人の叫ぶ声が聞こえた。驚いて立ち上がった鉄也が床板に頭をがつんとぶつけた。
目の前の浜を何人もの大人が走りすぎていく。
「オレらじゃないみたい」
ほっとして、亮一は頭をさすっている鉄也に言った。
怒鳴り声が海の方から聞こえてきた。
「 溺れとっぞ− !」
二人が急いで駆けつけると、大勢の大人が、そこだけ誰も泳いでいない濁った緑茶色の海を眺めていた。人混みの隅に、顔見知りの目の大きな若はげの警察官がいて、二人の高校生の腕を掴み、険しい顔で海を見つめていた。
坊主頭の二人の高校生の顔は、日焼けしているのに真っ青で、濡れた躰は炎天下なのに鳥肌が立っていた。顔中に水滴がまとわりついているのに拭おうともせず、怯えたように全身を小刻みに震わせていた。
まるで何度もタライの水に沈められ、ずぶ濡れで震えている鼠のようだ・・亮一の脳裏に、いつだったか鉄也の母ちゃんが鼠を水に沈めていた時の情景が浮かんだ。
海に彼らの友達が沈んでいる・・・亮一はそう気付いた。
水中メガネを付けた男が突然、海岸から十メートル離れた海面に浮かび上がってきた。男は日焼けした逞しい躰に、半紬シャツとバミューダーパンツといういでたちで岸にたどり着くと、
「駄目だ、見つからんじゃ」といって水中メガネを外した。シヤンハイのおっちゃんだった。
「とにかくみんなで、沖に流されんうちに探し出さんまいけ(探し出しましょう)」
シヤンハイのおっちゃんの指示に従って、十数人の大人たちが手をつないで一列になり、十メートル程沖の足の届くところまで海岸から連なった。濁った浅瀬を岸に沿って歩きながら、沈んだ高校生を足で探ろうというのだ。
亮一たちが列の端に加わろうとしたとたん、おっちゃんの太い声が飛んできた。
「ボウヤ、おまえらは駄目やちゃ。わしが戻るまで小屋の番をしとれ」
町内会長でもあるおっちゃんの命令は子供には絶対だった。亮一は名残借しそうな鉄也の手を引っ張って、シヤンハイのボート小屋へと引き上げた。町のほうから救急車のサイレンの音が近づいていた。