鉄也の機転に亮一は救われた気がした。
洋介もほっとしているようで、「失敗は成功の母だちゃ」と、わけのわからないことを言っておどけた。三人はカエルをビニール袋に入れて家を出た。
亮一たちの住む岩瀬古志町は海岸沿いにあった。
海岸線から砂浜を百メートル程隔てて、くっつき合うように建ち並ぶ家々は、ほとんどが潮風にさらされた赤茶けたトタン屋根と萎びた板張りの家だった。町の中心に二本だけ土の道が交差していたが、それ以外のところは砂地で、砂地に寄りそうひなぴた集落は、まあ言ってみれば、砂の町という風情だった。
鉄也は浜へ出る狭い路地を先頭に立って歩きながら、
「なんか、カエルもだけど、慎二にも悪いことしたのう」と言った。
亮一は、もとはといえば解剖を言い出したオレの責任なんだ、と心の中で呟いた。
路地から浜に出たところには、シーソーや滑り台などの遊具が、海岸線に沿って三十メートル間隔でポツンポツンと砂地に設置されていた。
三人は、鎖の高さが四メートルもある八台のブランコの、その支柱の傍らに、三十センチ位の深さの穴を手で掘ると、ビニール袋に入れたままのカエルを埋め、砂を盛り上げて小山をこしらえた。それからその辺にあった板切れを小山に差し、群生している浜昼顔の薄紫色の花を一本づつ手折って供えてから、三人並んで手を合わせた。
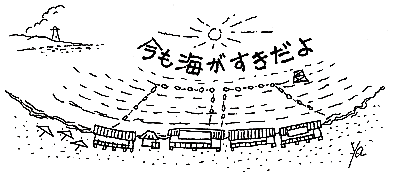
「おい、あそこ見ろ!」
洋介が突然海辺を指差した。二人が顔を上げて指差すほうを見ると、そこには建てかけの浜茶屋があった。そしてその向こうには材木を砂浜に運び込んでいるおじさんがいる。
「そっかあ、浜茶屋かあ」
亮一は自分で言った『浜茶屋』という言葉の響きに、なんともいい現わすことのできない喜びを感じた。
「そう、そう、もうすぐ夏休みだもんな」
鉄也が血がまだらに付いたシャツを脱いで裸になると、嬉しそうにシャツを振り回した。
亮一はふと、材木を運んでいるおじさんの向こうに、鉄也のおばあちゃんの姿を小さく見つけた。右手に細長い棒を持ち、左手にいくつかの白いボールを抱えているようだ。おばあちゃんはひまなときには、岸に打ち上げられるいろいろなゴミの中から、鉄也のために遊び道具を探していることがよくあった。細長い棒を、流木に絡まっているゴミに突っ込んで掻き回しているおばあちゃんのようすがなんだか可笑しくて、亮一はおもわず「くくっ」と笑った。
「どうしたが?」と鉄也が訊いた。
亮一はおばあちゃんのことは言わずに、建てかけの浜茶屋を見つめて、「もうすぐ夏休みだね」と、鉄也と同じことを言った。
「そう、そう、夏休み、夏休み。それに間違いござんせん」
鉄也は時代劇の言い回しで言うと、シャツを大きくひと振りして左肩に掛け、ニタリと口元で笑って見せた。